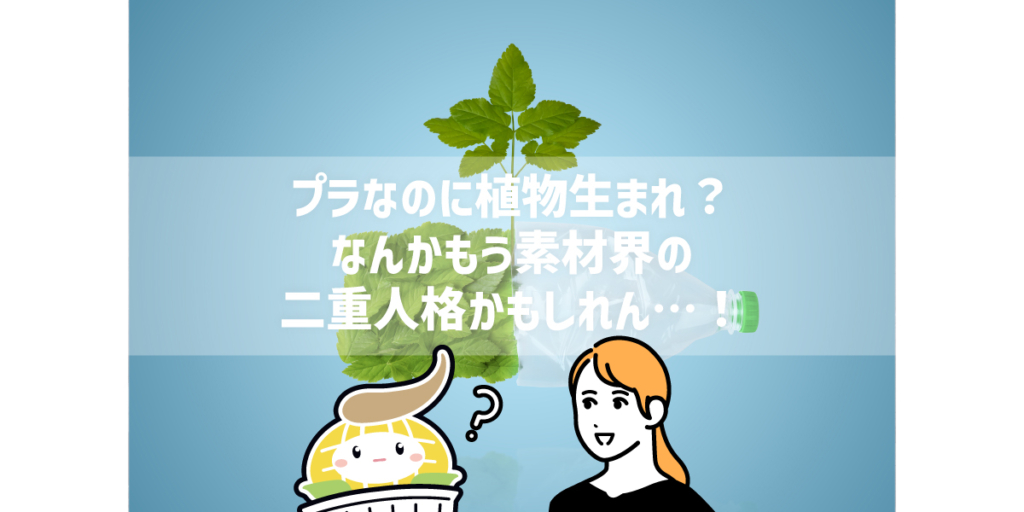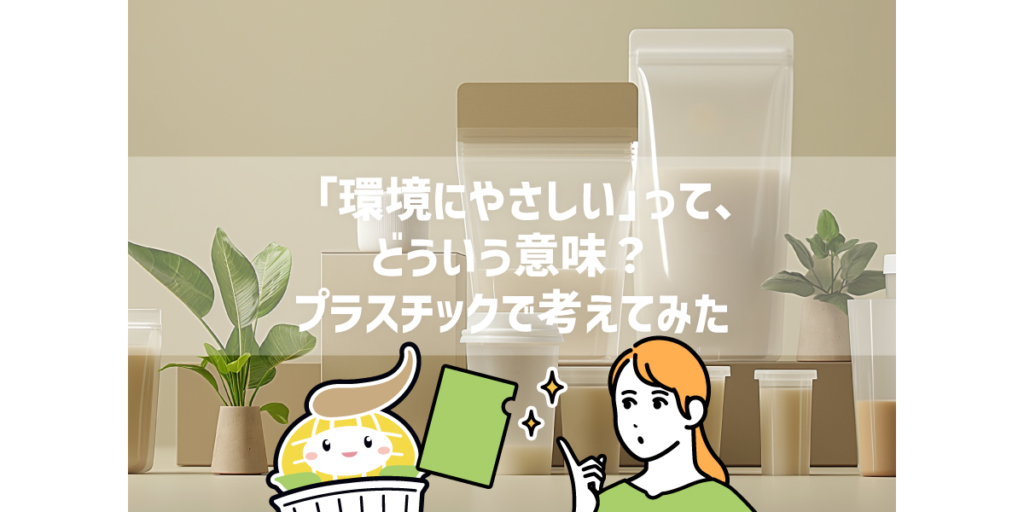コラム
2025/07/28
LCAだけじゃない!? エコ素材の“成績表”いろいろまとめてみた
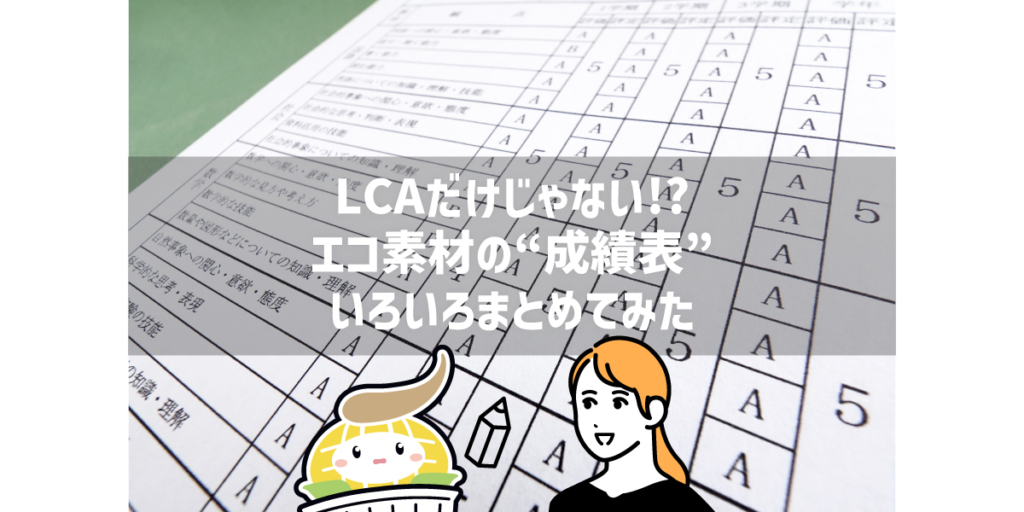
目次
"LCAだけじゃ足りない?" エコ素材選びの“迷子”になっていませんか?

環境配慮型素材を選定する際、多くの企業が「LCA(ライフサイクルアセスメント)」に注目しています。でも、実は…それだけじゃ、ちょっともったいないかもしれません!
たとえば、ある食品メーカーが「CO2排出量の少ない素材」としてLCAの数値を基に選定したのに、輸出先の国ではリサイクルインフラが未整備で、結局焼却処理になるというガーーン!な展開も。
今回は、そんな“LCAだけに頼る見方”を少し広げて、環境配慮素材――特に「バイオマスプラスチック」などの評価に使える“成績表”を大公開!LCAに加えて他の「見方」も整理しながら、素材選びをもっと柔軟に楽しんでみませんか?
環境配慮素材を評価する「成績表」はひとつじゃない

HP担当者
最近、「バイオマスプラスチックはLCAが良ければOK!」って声、よく聞くんですよね~。
えっ、一項目しか書かれてない成績表で全部決めちゃうレジ!? 他にも見ておきたいところ、あると思うレジ〜!

コバレジくん

HP担当者
そうなんだよね~!
素材の“エコ度”って、いろんな視点から見てみると、新しい気づきがあるかもしれないんだよね。
環境素材を評価するときには、下記のようにいくつかの基準で見ることができます。
- CO2排出量
- 再生可能資源の割合(=バイオマス度)
- 生分解性・堆肥化性
- リサイクル実績や回収性
- 消費者への伝わりやすさ(マーク、認証など)
うわぁ…見るところって、こんなに種類があるレジ!?びっくりレジ〜!

コバレジくん

HP担当者
そうなの。
目的や状況によって、どの成績表が必要になるかって、けっこう違ってくるんだよね。
代表的な環境評価指標(成績表)まとめ【5選】
① LCA(ライフサイクルアセスメント)

LCA(Life Cycle Assessment)は、原材料の採取から製品の製造、流通、使用、廃棄・リサイクルまで、いわゆる“製品の一生”すべてにおいて、どれだけ環境に負荷をかけているかを数値化・可視化する評価手法です。CO2排出量だけでなく、エネルギー消費や水使用量なども含めて定量的に評価できるのが特徴です。
- 具体例:同じ「バイオマスプラスチック製カップ」でも、原料の輸送距離が長かったり、成形時のエネルギー使用量が多ければ、LCA上の評価で差がつくことも。
- 活用場面:環境配慮設計(DfE)や国際的な取引(欧州向け輸出など)で重視されます。
- 関連規格:ISO 14040、14044。
えっ、原料がエコでも、輸送トラックがめっちゃ走ったら点数下がるレジ!?全体を見てるんだレジね~!

コバレジくん
② カーボンフットプリント(CFP)

CFP(Carbon Footprint of Products)は、製品1単位あたりの温室効果ガス排出量(CO2換算)を数値として算出し、ラベルなどで“見える化”する手法です。原料調達から製造、輸送、使用、廃棄までの工程で発生するCO2やメタン、亜酸化窒素といった温室効果ガスをCO2に換算して合算するのが特徴で、製品1個あたりにどれだけ地球温暖化への影響があるかを直感的に把握できます。
- 具体例:500mlの飲料用カップで「CFP:48g-CO2e」などと表示。近年では食品パッケージや文具、日用品などにも拡大中。
- 活用場面:消費者に向けた製品アピール、環境報告書、サステナビリティレポートなど。
- 関連制度:PAS 2050(英国)、ISO/TS 14067 など。

HP担当者
CFPは、数字が“見える化”されてるから、社内稟議にも強い味方なんですよね〜。
③ バイオマス度(バイオマスマークなど)

「バイオマス度」は、製品に含まれる炭素のうち、とうもろこしやサトウキビなどの再生可能な生物由来資源(バイオマス)に由来する炭素の割合(%)を示す指標です。たとえば、製品中の炭素のうち50%が植物由来であれば、「バイオマス度50%」と表記されます。
- 具体例:日本のバイオマスマーク制度では、10%以上のバイオマス含有で製品へのマーク表示が可能。当社の素材「Reseam ST」を用いた菓子トレーには、50%のマークを表示した製品も。
- 活用場面:官公庁調達基準(グリーン購入法)、認証制度、企業の環境配慮アピール。
- 注意点:“植物由来”という情報はあくまで原料の出どころを示すもので、「土に還るかどうか」とは別の話。
「植物から生まれた」って聞くとエコに思えるレジけど、それを公式にきちんと示すマークがあるんだレジね~!

コバレジくん

HP担当者
そうだね。バイオマスマークって、スーパーとかでもよく見かけるけど、ちゃんと意味を知るのも大事だね!
④ 生分解性・堆肥化適性(OK compost、ASTM D6400 など)

生分解性とは、微生物の働きによって、素材が最終的に水と二酸化炭素にまで分解される性質のことです。一方、堆肥化可能とは、産業用コンポスト施設など、特定の温度・湿度・時間といった条件下で分解され、有機肥料(堆肥)として利用可能になることを意味します。
- 具体例:OK compost(TÜV AUSTRIA)認証では、その素材(製品)が工業用コンポスト施設において90日以内に90%以上分解されることを保証します。
- 活用場面:飲食テイクアウト容器、海外輸出品(特に欧州)、イベント用資材など。
- 注意点:常温の屋外や自然の中にそのまま置いておけば分解される、というわけではない。特に生分解性プラスチックの多くは、専用の産業用コンポスト施設など、特定の環境条件がそろわないと分解が進まないものが多いため、「海に捨てても大丈夫」と思われがちだが、そうした誤解には注意。

HP担当者
この誤解、けっこう多いんですよね…。
「本当に地球にやさしいの?」と感じたときは、条件までしっかりチェックしてみてくださいね。
⑤ リサイクル適性・アップサイクル実績

リサイクル適性とは、その素材がどれだけ分別しやすく、効率的に回収・再資源化できるかを示す指標です。たとえば、単一素材でできていたり、異なる素材との分離がしやすい場合は、リサイクルの難易度が下がります。
また、アップサイクル実績とは、回収された素材が実際にどのような製品として再利用されたかという、具体的な活用例の有無を指します。
- 具体例:ショッピングモールで回収した衣料用ハンガーを粉砕・再成形し、什器や店内サインとして再活用する等の取り組み事例があります。
- 活用場面:自治体連携・店頭回収型施策、地域循環のPR、リサイクル対応の認証制度など。
- 注意点:素材そのものの特性だけでなく、使用後の回収体制や加工設備といった「運用の仕組み」と合わせて考えることが大切。

HP担当者
ちなみに、宮城県の東松島市では、弊社のバイオマスプラスチック「Reseam ST」を用いた食品容器の回収スキームが実施されて、回収された容器はキーホルダーにアップサイクルされたんですよ~!
それってまさに“再登場”レジ!
ぼくも現場でがんばったから、うれしいレジ〜!

コバレジくん
実際にどう選ばれている?企業の素材選定事例

HP担当者
素材選びって、業界によって“持っておきたい成績表”がまったく違うんですよね。
たしかに、毎回全部の成績表を取り寄せてチェックしていたら大変レジ…

コバレジくん
たとえば:
- 食品包装業界(欧州向け輸出あり) → LCA+CFP表示はマスト。エビデンス命!
- ローカルな外食チェーン → 「店舗回収→アップサイクル」による循環PRが効果的かも?
- 化粧品業界 → パッケージの“見た目のサステナブル感”も重要。生分解性や、バイオマスマーク表示が人気!
同じ「バイオマスプラスチック」を使うタイミングでも、こうも違うとは!驚きレジ!

コバレジくん

HP担当者
素材を選ぶときは、「何をどんなふうにアピールしているか」にも注目してみるといいかもね。
まとめ:“うちに合った”エコ指標を選ぶ視点
素材選びには、正解がひとつだけあるわけではありません。
素材評価の指標は「どれが1番いいか」ではなく、「どれがうちに合うか」を見つけることが大切です。
LCAに加えて、今回紹介した様々な“見方”を組み合わせることで、もっと柔軟で前向きな素材選びができるかもしれません。

HP担当者
LCAだけにこだわらずに、いろんな視点で素材を見るのって、選ぶ側にとってもチャンスが広がりますね!
ぼくの普段の努力も、ちゃんと“成績表”に書いてあったのかも…レジ?
ちなみにぼく、最近努力賞もらったレジ〜!!(ドヤ)

コバレジくん

HP担当者
(誰が努力賞をあげたんだ…⁉)
よ、よかったねコバレジくん!そういう“がんばり”がちゃんと伝わる成績表があると、みんなにもコバレジくんのよさが伝わるかもしれないね~!
評価軸選び、迷ったら
バイオマスプラスチックの導入をご検討中の方へ:
「用途や戦略に合った評価軸をどう設計すればいいか」についてなど、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください!